【週刊 太宰治のエッセイ】諸君の位置

今週のエッセイ
◆『諸君の位置』
1940年(昭和15年)、太宰治 31歳。
1940年(昭和15年)2月上旬に脱稿。
『諸君の位置』は、1940年(昭和15年)3月30日発行の「月刊文化学院」第二巻第二号(№9)に発表された。なお、同誌の表紙には「二月二十日印刷納本、二月二十三日発行」とある。「三月」は「二月」の誤植とも考えられる。『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)では、奥付の「三月三十日」という表記に準拠している。
「諸君の位置」
世の中の。どこに立って居るのか、どこに腰掛けて居るのか、甚 だ曖昧なので、学生たちは困って居る。世の中のことは何も知らぬふりして無邪気をよそおい、常に父兄たちに甘えて居ればいいのか。又は、それこそ、「社会の一員」として、仔細 らしい顔をし、世間の大人の口吻 を猿真似して、大人の生活の要らざる手助けに努めるのがいいのか。いずれにしても不自然で、くすぐったく、落ちつかないのである。諸君は、子供でも無ければ、大人でも無い。男でも無ければ、女でも無い。埃 っぽい制服に身を固めた「学生」という全然特殊の人間である。それはまるで、かの半人半獣の山野の神、上半身は人間に近く、脚はふさふさ毛の生えた山羊の脚、小さい尻尾をくるりと巻き、頭には短い山羊の角を生 して居るパン、いやいや、パンは牧羊神として人々にも親しまれた音楽の天才であり笛がうまいし、葦笛を発明するほどの怜悧明朗の神であるが、学生諸君の中には、此のパンと殆ど同一の姿をして居ながら、暗い醜怪の心のサチイル、即ち憂鬱淫酒の王ディオニソスの竉児さえ存在するのだ。我が身が濁って低迷し、やりきれない思いの宵も、きっと在る。諸君は一体、どこに座って居るのか、何をみつめて居るのか。先日、或る学生に次のようなシルレルの物語詩を語って聞かせたところ、意外なほどに、其の学生は喜んだ。諸君は、今こそ、シルレルを読まなければなるまい。素朴の叡智が、どれほど強力に諸君の進路を指定してくれるものであるかを知るであろう。
「受け取れよ、世界を!」ゼウスは天上から人間に呼びかけた。「受け取れ、これはお前たちのものだ。お前たちにおれは之を遺産とし、永遠の領地として贈ってやる。さあ、仲好く分け合うのだ。」忽 ち先を争って、手のある限りの者は四方八方から走り集った。農民は、原野に縄を張り廻し、貴公子は、狩猟のための森林を占領し、商人は物貨を集めて倉庫に満し、嘲弄は貴重な古い葡萄酒を漁り、市長は市街に城壁を廻 らし、王者は山上に大国旗を打ち樹てた。それぞれ分割が、残る隈なくすんだあとで、詩人がのっそりやって来た。彼は、遥か遠方からやって来た。ああ、その時は、地球の表面に存在するもの悉 くに其の持主の名札が貼られ、一坪の青草原さえ残っていなかった。「ええ情ない! なんで私一人だけがみんなから、かまって貰えないのだ。この私が、あなたの一番忠実な息子が?」と大声に苦情を叫びながら、彼はゼウスの玉座の前に身を投げた。「勝手に夢の国でぐずぐずして居て、」と神はさえぎった。「何もおれを怨むわけが無い。お前は一体どこに居たのだ。みんなが地球を分け合って居るとき。」詩人は泣きながらそれに答えて、「私は、あなたのお傍に。目はあなたの顔にそそがれて、耳は天上の音楽に聞きほれて居ました。この心をお許し下さい。あなたの光に陶然と酔って、地上のことを忘れて居たのを!」「どうすればいい?」とゼウスは言った。「地球はみんな呉れてしまった。秋も、狩猟も、市場も、もうおれの物でない。お前がこの天上におれと一緒に居たいなら、時々やって来い。此所はお前の為に空けて置く!」
詩は、それでおしまいであるが、此の詩人の幸福こそ、また学生諸君の特権でもあるのだ。これを自覚し、いじけず、颯爽と生きなければならぬ、実生活に於ける、つまらぬ位置や、けちくさい資格など、一時、潔く放棄してみるがよい。諸君の位置は、天上に於て発見される。雲が、諸君の友人だ。
無責任に大げさな、甘い観念論で、諸君を騙そうとして居るのでは無い。これは、最も聡明な、実状に即してさえいる道である。世の中に於ける位置は、諸君が学校を卒業すれば、いやでもそれは与えられる。いまは、世間の人の真似をするな。美しいものの存在を信じ、それを見つめて街を歩け。最上級の美しいものを想像しろ。それは在るのだ。学生の期間にだけ、それは在るのだ。もっと、具体的に言い度 いが、今日は何だか腹立たしい。君たちは何をまごまごして居るのか、どんと背中をどやしつけてやり度い思いだ。頭の悪い奴は、仕様がない。チェホフを、沢山読んでみなさい。そうしてそれを真似して見なさい。私は無責任なことは言って居ない。それだけでもまずやってみなさい。少しは、私の言うこともわかるようになるかもしれない。
失礼なことばかり言いました。けれども、こんな乱暴な言い方でもしないことには、諸君は常にいい加減に聞き流すことに馴れて居る。諸君の罪だけではないけれども。
太宰とシルレル
今回紹介したエッセイで、太宰は「諸君は、今こそ、シルレルを読まなければなるまい」と書いています。「シルレル」というと、このエッセイとほぼ同時期に執筆された太宰の小説『走れメロス』の末尾にも、「(古伝説と、シルレルの詩から。)」と書かれていました。
「シルレル」とは、ドイツの詩人、歴史学者、劇作家、思想家であるヨーハン・クリストフ・フリードリヒ・フォン・シラー(1759~1805)のこと。ゲーテと並ぶドイツ古典主義の代表者です。劇作家として有名だが、ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付き」の原詩が最も知られているように、詩人としても有名です。
シラーの書く詩は、非常に精緻かつ優美であるといわれ、「ドイツ詩の手本」として、今なおドイツの教育機関で教科書に掲載され、生徒によって暗誦されているそうです。

■フリードリヒ・フォン・シラー(1759~1805)
「先日、或る学生に次のようなシルレルの物語詩を語って聞かせたところ、意外なほどに、其の学生は喜んだ」と言う太宰ですが、太宰もシラーの詩を読んで、小説『走れメロス』を執筆しました。
『走れメロス』の元になった伝承は、古代ギリシャ・ピタゴラス派の教団員の間の団結の固さを示す逸話として発生したものと言われています。ピタゴラス派は、宗教・政治団体の性格を持つ秘密結社を組織しており、構成員は財産を共有して共同生活を行い、強い友愛の絆で結ばれていることで知られていました。
太宰は、ドイツ文学者・小栗孝則(1902~1976)が1937年(昭和12年)7月に翻訳した『新編シラー詩抄』(改造文庫)に収録されてる「人質」を参考に、『走れメロス』を執筆しました。小栗は、訳注に「メロスの友人の名がセリヌンティウスである」ということを記しており、太宰の言う「古伝説」とは、これを指しています。
小栗が翻訳した「人質」を、以下に引用します。なお、旧仮名づかいは、新仮名づかいに改め、旧字体で書かれているものは、原則として新字体に改めました。
「人質」訳詩
暴君ディオニスのところに
メロスは短剣をふところにして忍びよった警吏 は彼を捕縛した
「この短剣でなにをするつもりか? 言え!」
険悪な顔をして暴君は問いつめた
「町を暴君の手から救うのだ!」
「磔 になってから後悔するな」――
「私は」と彼は言った「死ぬ覚悟でいる
命乞いなぞは決してしない
ただ情けをかけたいつもりなら
三日間の日限をあたえてほしい
妹に夫をもたせてやるそのあいだだけ
その代り友達を人質として置いておこう
私が逃げたら、彼を絞め殺してくれ」
それを聞きながら王は残虐な気持で北叟笑 んだ
そして少しのあいだ考えてから言った
「よし、三日間の日限をおまえにやろう
しかし猶予はきっちりそれ限りだぞ
おまえがわしのところに取り戻しに来ても
彼は身代りとなって死なねばならぬ
その代り、おまえの罰はゆるしてやろう」
さっそくに彼は友達を訪ねた。「じつは王が
私の所業を憎んで
磔の刑に処すというのだ
しかし私に三日間の日限をくれた
妹に夫をもたせてやるそのあいだだけ
君は王のところに人質となっていてくれ
私が縄をほどきに帰ってくるまで」
無言のままで友と親友は抱きしめた
そして暴君の手から引き取った
その場から彼はすぐに出発した
そして三日目の朝、夜もまだ明けきらぬうちに
急いで妹を夫といっしょにした彼は
気もそぞろに帰路をいそいだ
日限のきれるのを怖れて
途中で雨になった、いつやむともない豪雨に
山の水源地は氾濫し
小川も河も水かさを増し
ようやく河岸にたどりついたときは
急流に橋は浚 われ
轟々とひびきをあげる激浪が
メリメリと橋桁 を跳ねとばしていた
彼は茫然と、立ちすくんだ
あちこちと眺めまわし
また声をかぎりに呼びたててみたが繋舟 は残らず浚 われて影なく
目ざす対岸に運んでくれる
渡守りの姿もどこにもない
流れは荒々しく海のようになった
彼は河岸にうずくまり、泣きながら
ゼウスに手をあげて哀願した
「ああ、鎮めたまえ
荒れくるう流れを!
時は刻々に過ぎてゆきます、太陽もすでに
真昼時です、あれが沈んでしまったら
町に帰ることが出来なかったら
友達は私のために死ぬのです」
急流はますます激しさを増すばかり
波は波を捲 き、煽りたて
時は刻一刻と消えていった
彼は焦燥にかられた、ついに憤然と勇気をふるい
咆え狂う波間に身を躍らせ
満身の力を腕にかけて流れを掻きわけた
神もついに憐愍 を垂れた
やがて岸に這いあがるや、すぐにまた先きを急いだ
助けをかした神に感謝しながら――しばらく行くと突然、森の暗がりから
一体の強盗が踊り出た
行手に立ちふさがり、一撃のもとに打ち殺そうといどみかかった
飛鳥のように彼は飛びのき
打ちかかる弓なりの棍棒を避けた
「何をするのだ?」驚いた彼は蒼くなって叫んだ
「私は命の外には何も無い
それも王にくれてやるものだ!」
いきなり彼は近くの人間から棍棒を奪い
「不憫だが、友達のためだ!」
と猛然一撃のうちに三人の者を
彼は仆 した、後の者は逃げ去った
やがて太陽が灼熱の光りを投げかけた
ついに激しい疲労から
彼はぐったりと膝を折った
「おお、慈悲深く私を強盗の手から
さきには急流から神聖な地上に救われたものよ
今、ここまできて、疲れきって動けなくなるとは
愛する友は私のために死なねばならぬのか?」
ふと耳に、潺々 と銀の音色のながれるのが聞こえた
すぐ近くに、さらさらと水音がしている
じっと声を呑んで、耳をすました
近くの岩の裂け目から滾々 とささやくように
冷々とした清水が涌きでている
飛びつくように彼は身をかがめた
そして焼けつくからだに元気を取りもどした
太陽は緑の枝をすかして
かがやき映える草原の上に
巨人のような木影をえがいている
二人の人が道をゆくのを彼は見た
急ぎ足に追いぬこうとしたとき
二人の会話が耳にはいった
「いまごろは彼が
磔にかかっているよ」
胸締めつけられる想いに、宙を飛んで彼は急いだ
彼を息苦しい焦燥がせきたてた
すでに夕映の光りは
遠いシラクスの塔楼のあたりをつつんでいる
すると向うからフィロストラトスがやってきた
家の留守をしていた忠僕は
主人をみとめて愕然とした
「お戻りください! もうお友達をお助けになることは出来ません
いまはご自分のお命が大切です!
ちょうど今、あの方が死刑になるところです
時間いっぱいまでお帰りになるのを
今か今かとお待ちになっていました
暴君の嘲笑も
あの方の強い信念を変えることは出来ませんでした」――
「どうしても間に合わず、彼のために
救い手となることが出来なかったら
私も彼と一緒に死のう
いくら粗暴なタイラントでも
友が友に対する義務を破ったことを、まさか褒めまい
彼は犠牲者を二つ、屠 ればよいのだ
愛と誠の力を知るがよいのだ!」
まさに太陽が沈もうとしたとき、彼は門にたどり着いた
すでに磔の柱が高々と立つのを彼は見た
周囲に群衆が憮然として立っていた
縄にかけられて友達は釣りあげられてゆく
猛然と、彼は密集する人ごみを掻きわけた
「私だ、警吏!」と彼は叫んだ「殺されるのは!
彼を人質とした私はここだ!」
がやがやと群衆は動揺した
二人の者はかたく抱き合って
悲喜こもごも気持で泣いた
それを見て、ともに泣かぬ人はなかった
すぐに王の耳にこの美談は伝えられた
王は人間らしい感動を覚えて
早速に二人を玉座の間に呼びよせた
しばらくはまじまじと二人の者を見つめていたが
やがて王は口を開いた。「おまえらの望みは叶ったぞ
おまえらはわしの心に勝ったのだ
信実とは決して空虚な妄想ではなかった
どうかわしをも仲間に入れてくれまいか
どうかわしの願いを聞き入れて
おまえらの仲間の一人にしてほしい」
大まかなストーリーは『走れメロス』にそのまま受け継がれていますが、有名な冒頭「メロスは激怒した。」などの印象的なフレーズは、太宰の創作であることが分かります。太宰が細部に凝らした創作部分を、『走れメロス』と読み比べながら探してみるのも面白いのではないでしょうか。
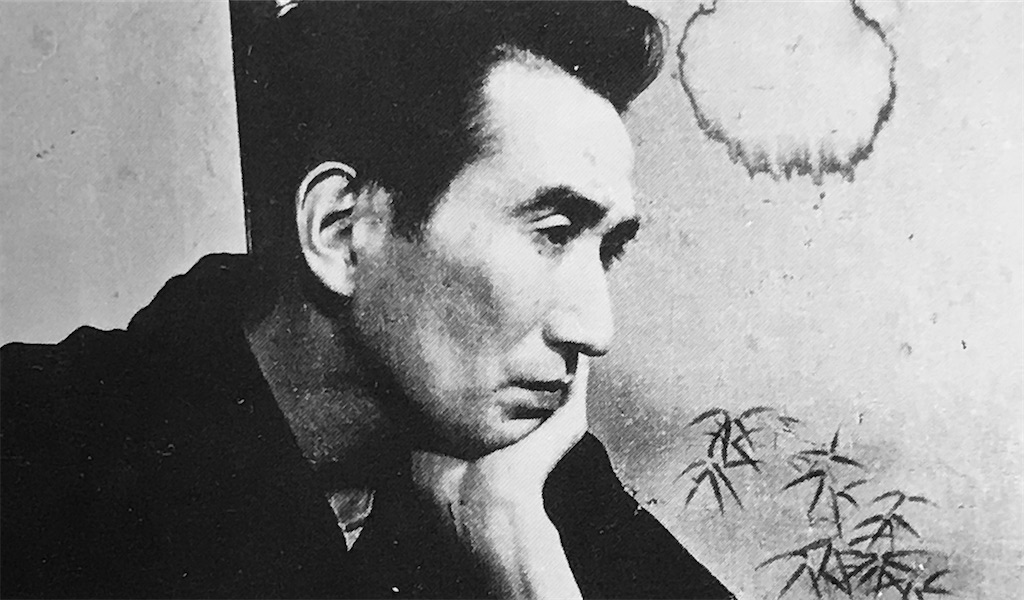
また、『走れメロス』を執筆するにあたって、インスピレーションを与えたのではないか?と言われている「熱海事件(付け馬事件)」と呼ばれる事件も、1936年(昭和11年)12月末に起こっています。
【了】
********************
【参考文献】
・小栗孝則 訳『新編シラー詩抄』(改造文庫、1937年)
・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)
・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)
・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)
※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。
********************
【太宰治39年の生涯を辿る。
"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】
【太宰治の小説、全155作品はこちら!】
【週刊 太宰治のエッセイ】知らない人

今週のエッセイ
◆『知らない人』
1940年(昭和15年)、太宰治 31歳。
1940年(昭和15年)2月上旬頃に脱稿。
『知らない人』は、1940年(昭和15年)3月1日発行の「書物展望」第十巻第三号の「随筆」欄に発表された。この欄には、ほかに「平林寺へ」(中塚一碧楼)、「枲山閣叢話(三)」(樋口龍太郎)、「鋏と糊と蚕拂い」(木寺相模)、「机の塵」(湯朝竹山人)、「古本懐舊話題」(鳥東吉)が掲載された。
「知らない人」
ことしの正月は、さんざんでありました。五日すぎから、腰の右方に腫物ができて、粗末にしていたら次第にそれが成長し、十五日までは酒を呑んだりして不安の気持をごまかしていましたが、とうとう十六日からは、寝たっきりになってしまいました。悪寒疼痛、ニ、三日は、夜もろくに眠れませんでした。手術は、いやなので無二膏 という膏薬 を患部に貼り、それだけでも心細いので、いま流行しているらしい、れいの「二箇のズルフォンアミド基」を有する高価の薬品を内服してみました。葡萄状球菌、連鎖状球菌に困る諸疾患にも卓効を奏するということだったので、私は、それを、はじめて二錠服用したときから、既に恢復 の一歩を踏み出したような爽快を覚えました。私は、膏薬の効能書を、実に信用する愚かな性質を持って居ります。その、「二箇のズルフォンアミド基」を有する高級化学療法剤に就いては、かねて新聞広告に依っても承知していたのでありますし、いま自ら購 い求めて、薬品に添付されて在る一枚の効能書をつくづく眺め、熟読して、腰の腫物を忘却してしまうほど安心したのであります。効能書に依れば、これは、たいした薬なのであります。世界を驚かした大発明なのであります。私は、ここでその薬品の広告をするつもりでは無いから、くわしくは書きませんが、実に種々雑多の難病に卓効を奏する薬なのであります。もう、これで、なおった。腫物が、なおるばかりでなく、肌がなめらかになり色が白くなるかも知れない、と家の者に冗談を言い、静かに横臥 し、薬のききめを待っていました。二錠ずつ、一日三回服用すると、たいていの腫物は、なおるという効能書の言葉だったのですが、二日服用しても、三日服用しても、ちっとも軽快になりません。おなかが変に張って、ごろごろ鳴ります。胃に悪い薬のようです。三日服用したら、あと服用を禁止せよ、三日乃至 五日間休止して、それからさらに二錠ずつの服用を開始せよ、と効能書に書かれて在りましたので、私は、少しも、ききめの無いままに、その薬の服用を、やめなければならなくなりました。すでに私は、三日間、服用してしまったのです。甚 だ、味気ない思いでありました。腫物はいよいよ発展し、いまは膏薬では間に合わず、脱脂綿に無刺激の油薬を塗って患部に貼りつけ、日に五、六回も貼りかえなければなりませんでした。膿が、どんどん出るのです。その状は、流石に形容を遠慮しますけれど、とにかく酸鼻の極でありました。お銚子の底くらいの大きい深い穴が腰にぽっかりできてしまったのです。入院、ということも考えましたが、それでも、やはり心の奥底で、かの高価な「二個のズルフォンアミド基」を有する世界的な新薬を、たのしみにしているところが在るらしく、そのうち卓効を奏するであろうと、身動きもならず静かに横臥して、天に祈る気持でありました。服用休止の三日間が過ぎて、さらに私は新薬の服用を開始しました。いたずらに膿が流出するだけであります。患部を見ると、あまりの惨状にくらくら眩暈 を感じます。腫物で死ぬ奴も無いだろう、などと強がりを言って、医者に見せようともしませんでしたが、どうも、夜半ひとり眼覚めて、いろいろのことを考えると、なかなかに心細くなるのでした。寝ついてから、もう十日以上になります。いまは、膿も、あまり出なくなって、からだも軽くなり、こうして床に腹這いになり原稿を書けるようになりました。だんだん、よくなって行くのでしょう。やはり、「二個のズルフォンアミド基」のおかげなのでしょうか。それにしても、ずいぶん緩慢な卓効ぶりであります。全快までには、まだまだ相当の日数がかかるような気がします。私が、あまり有頂天で効能書の文句を信じ過ぎたのでありましょう。現実は、たいてい、こんなものではないでしょうか。この世に、奇跡なんてものを期待した私は、ばかであります。
十日間、寝たままなので、ずいぶん本を読みました。なんでもかでも、選択せずに読みました。恵送された同人雑誌も、全部読破しました。一つ、心に残った記事があります。第一早稲田高等学院の「学友会雑誌」に、K教授の追悼記が載っていました。K教授という人は、どんな人だか、私はちっとも存じません。逢ったことも無し、また、名を聞いたことさえありません。けれども、その雑誌に載っている四つの追悼記を読んで、実にその人を、なつかしく、惜しく思いました。こんな美しい人も生きていたのかとほのぼの楽しく、また、もうこの人も、なくなって、お逢いできる望みは、全く無いのだと思うと、胸ががらんどうになって侘びしく、鬱な気持でありました。四人の人が、追悼文を書いているのですが、その四人の人の名も、私は知っていません。四人とも、早稲田の先生なのでしょう。私の知らない人ばかりですが、なかなか巧みに書いて居ります。追悼文を読み、私のように故人を全く知らぬ男にさえ、故人に対して追慕の念を懐かせるのは、それは、きっと追悼文の誠実さであり、またその追悼文の筆者の故人に対する深い愛情の証拠であると考えられますが、また、それだけ故人の徳の深さをも思いやられるところが在るのであります。つまり、故人の徳の深さが、このように友人たちに、美しい追悼文を書かせた、という交互相照の作用を考えることもできるのであります。私は、終りのほうから逆に読んで行きました。一ばん終りには、Y・Tという人が、「K君は歩きながら語り合う様な人であった。さし向って話すときでもお互いにそっぽをむいて話した。それが大変に気持よかった。そして黙ったままでいても気持が良かった。」と書いています。また、「勢いこんで議論を吹きかけるとK君は大抵だまって、ものの十秒も考えてから言うのである。君の言うことも、そう、そんなこともあるよ、とK君は独特のアクセントで言ってたいてい賛成してくれる。K君は気の弱い人である。恐らく沢山の人がK君を軽んじていたと思う。それは全く、はたで見ていて歯がゆくなる程であった。K君は決して他人の悪口を言わない。他人の批評をしない。決して蔭口をきかない。けれども、厭なもの、くだらぬものの傍は黙って通りすぎる人であった。云々。」とその他たくさんのいいことを書いているのです。М・Kという人が、その前の頁 に書いています。「実際あのひとの慇懃鄭重 は、生れつきだったらしい。幹部候補生を勤め上げて、騎兵少尉になってからのことだ。どこかへ演習に行って帰る時、集合命令をかけたが、雑談に余念のなかった二三の部下に徹底しなかった。つかつかと歩み寄ったK少尉、いきなりのびんた の一つも張るかと思ったらさにあらず、『それ位にして置いて早く集って下さい、済まんが』とやったものだ。部下は飽気 にとられる。側にいた上官が、そんなことで威厳が保てるか、と真赤になってK少尉の膏 を搾ったというが、Kさんは、そんな人だ。決して威張れない人なんだ。それでいて結構つよい反面もあって、学問上の議論となると、なかなか譲らない。我武者羅に押通そうものなら、黙って聴いてはいるが、『そういうけどなあ』とねちねちやって来る。言い出したら引かない。しまいには辞引きを出して来る。参考書を引張り出す。そうなったら大抵の場合、こちらの敗けだ。よく読んでいるからなあ。」と書いています。また、「本当の意味のユーモアは、K君の持味だった。軽口を言わず、駄洒落を飛ばさないから、K君をユーモリストだと誰も思わないけれど、挨拶をさせたり、序文を書かせたりしたら、K君のものは天下一品だ。少し長すぎるなと思っても、結構、しまいまで附合いさせる面白さがあった。微笑は、する者にも見る者にも、上品でよいものだ。そんな軽い微笑をK君は絶えず人々に、そっと投げかけていた。だからK君のいる傍は、いつも和やかな春風が吹いていた。云々。」その前の頁 には、D・Eという人が、「彼には、自分が生きるために、止むを得ず他の人間を喰物にするなぞという事は、誠に思いもよらぬ事の如くであった。気づかぬふりして人に迷惑をかける、なぞという事は絶対に彼の本性が許さなかった。彼は実に不便な思いをしながらも、最も人に迷惑をかけないような身の置き所から、身の置き所へと、恰 も飛石づたいのように拾い歩かなければならなかったのである。」と愛情を以て説明して居ります。また、その前の頁 には、T・Iという人が、「変な言いかたかも知れないが、Kさんは、ほんと の声を出す人であった、そうしてほんとの声しか、出さない人であった。君が純真率直で自己を偽れない人であった他面に、そういう人に時々見掛けられる他の人に対する冷酷さというものが殆 ど無く、反対に優しい心根の、先輩に対しては極めて謙譲な、実に美しい性情の持主であったことは、矢張り君の自己教養の深さから来たものではないかと思う。」と書いて、その実例を三つ四つ、引いて在るのです。実にK氏は、いい人だ、できた人だ。こんないい人が、どうして死んだのだろう、と追悼記の一ばん前の頁 をひらいて見ると、そこに、学院長K・Мという人の弔辞が在ります。「第一早稲田高等学院教授陸軍騎兵中尉K・K君逝けり。君は昨年九月召に応じて征途に就き、南支バイアス湾上陸軍に加わり、広東攻略戦に参加して奮闘せしが、幾ばくもなく病に罹 りて、戦線より後退するの止むなきに至り、爾来 台湾に、後広島に加療し、更に東京日本赤十字病院に転じて、只管に健康の恢復に力めしが、天無情にして齢を君に仮さず、客月二十九日、痛ましくも終に不帰の客となれり。云々。」と書いてありましたので、私は、なんだか、寝床に起き直りたい気持になりました。
小さい、美しい奇跡を、眼の前に見るような気がいたしました。奇跡は、やはり在るのです。
太宰の追悼文
今回紹介したエッセイ『知らない人』では、太宰が腫物に困り、横臥している間に読んだという、第一早稲田高等学院の「学友会雑誌」に掲載されていた、K教授の追悼記について書かれていました。
太宰は「故人の徳の深さが、このように友人たちに、美しい追悼文を書かせた、という交互相照の作用を考えることもできるのであります」と書いていますが、太宰の追悼文は、どうだったのでしょう。
太宰の葬儀の際には葬儀委員長を務め、太宰が尊敬し、心から甘えることができた数少ない先輩作家の1人である、

■
昭和二十三年四月二十五日、日曜日の、午後のこと、電話があった。
「太宰ですが、これから伺っても、宜しいでしょうか。」
声の主は、太宰自身でなく、さっちゃんだ。――さっちゃんというのは、吾々 の間の呼び名で、本名は山崎富栄さん。
日曜日はたいてい私のところには来客がない。太宰とゆっくり出来るなと思った。
やがて、二人は現われた。――考えてみるに、太宰は三鷹にいるし、私は本郷にいるので、時間から推して、お茶の水あたりからの電話だったらしい。伺っても宜しいかというのは一応の儀礼で、実は私の在否を確かめるためのものであったろうか。
「今日は愚痴をこぼしに来ました。愚痴を聞いて下さい。」と太宰は言う。
彼がそんなことを言うのは初めてだ。いや、彼はなかなかそんなことを言う男ではない。心にどんな悩みを持っていようと、人前では快活を装うのが彼の性分だ。
私は彼の仕事のことを聞いた。半分ばかり出来上がったらしい。――彼はその頃、「展望」に連載する小説「人間失格」にとりかかっていた。筑摩書房の古田氏の世話で、熱海に行って前半を書き、大宮に行って後半を書いたが、その中間、熱海から帰って来たあとで私のところへ来たのである。私は後に「人間失格」を読んで、あれに覗き出してる暗い影に心打たれた。あの暗い影が、彼の心に深く積もっていたのだろう。
しかし、愚痴をこぼしに来たといいながら、それだけでもう充分で、愚痴らしいものを太宰は何も言わなかった。――その上、すぐ酒となった。
だいたい
吾々 文学者は、少数の例外はあるが、よく酒を飲む。文学上の仕事は、我と我身を切り刻むようなことが多く、どうにもやりきれなくて酒を飲むのだ。または、頭の中、心の中に、いやな滓 がたまってきて、それを清掃するために酒を飲むのだ。太宰もそうだった。その上、太宰はまた、がむしゃらな自由奔放な生き方をしているようでいて、一面、ひどく極 りわるがり恥しがるところがあった。口を開けば妥協的な言葉は言えず、率直に心意を吐露することになるし、それが反射的に気恥しくもなる。そして照れ隠しに酒を飲むのだ。人と逢えば、酒の上でなえればうまく話が出来ない。そういうところから、つまり、彼は二重の酒を飲んだ。彼と逢えば私の方でも酒がなくては工合いがわるいのだ。
折よく、私のところに少し酒があった。だが、私のこの近所、自由販売の酒類はすぐに売り切れてしまう。入手に甚 だ困難だ。太宰はさっちゃんに耳打ちして、電話をかけさせる。日曜日でどうかと思われるが、さほど遠くないところに、二人とも懇意な筑摩書房と八雲書店とがある。
「もしもし、わたし、さっちゃん……。」そう自分でさっちゃんは名乗る。太宰さんが豊島さんところに来ているが、お酒が手にはいるまいかとねだる。お代は原稿料から差引きにして、と言う。――両方に留守の人がいた。八雲から上等のウイスキーが一本届けられ、夜になって、筑摩からも上等のウイスキーを一本、臼井君が、自分で持参された。
元来、太宰はひとに御馳走することが好きで、ひとから御馳走になることが嫌いだ。旧家大家に育った生れつきの心ばえであろうか。――嘗 て、生家と謂わば義絶の形となり、原稿もまだあまり売れず、困窮な放浪をしていた頃、右の点について、彼はずいぶん屈辱的な思いをしたことであろう。
私は太宰と懇意になったのは最近のことだが、私のところへ来ても、彼はいつも私へ御馳走しようとした。貧乏な私に迷惑をかけたくないとの配慮もあったろう。年長の私に対して礼をつくすという気持ちもあったろう。――彼が甘んじて世話になったのは、恐らく、死後も面倒をみて貰うことになった三社、新潮と筑摩と八雲であったろうか。
あの日も太宰は酒を集めてくれた。ばかりでなく、さっちゃんをあちこちに奔走さして、いろいろな食物を買って来さした。私の娘が結婚後も家に同居していて、その頃病気で伏せっていたのへも、お見舞として、バタや缶詰の類を買って来さした。
おかしいのは、鶏の料理だ。だいぶ前、太宰が来た時、私は目の前で鶏を料理してみせたことがある。へんな鶏で、雌雄がわからず、つまり、子宮も睾丸も摘出できなかったという次第で、大笑いとなった。こんな血腥 いこと、太宰としては厭だったろうと思われるのに、案外、彼は興味を持って、其 後、よそで、自ら執刀し、そこら中を血だらけにしたという。私はそれを聞いていたし、前回の失敗を取返したくも思い、丸のままを一羽求めて来さして、食卓の上で手際よく解剖してみせた。ところがその鶏、産むまぎわの卵を一つ持っていて、まだ殻がぶよぶよしてる大きいのが出て来て、私も、むろん太宰も、ちょっと面喰った。
酒の席まで文学論をやることは、太宰も私も嫌いだ。政治的な時事問題なども面白くない。話はおのずから、天地自然のこと、つまり山川草木のことが主となる。以前に、太宰と近所を歩いて、雀の巣だった銀杏の樹のあたりを通りかかったことがある。今ではその辺は戦災の焼跡になっているが、その銀杏の樹に
嘗 て、数百数千の雀が群がって囀 ずり、付近の人々は払暁 から眼を覚まされたという。その銀杏の樹が五本立ち並んでると私が言ったところ、三本しか見えないと太宰に指摘された。見ると、なるほど三本のようである。豊島さんの話、まったく出たらめで、五本だと言うが、なあに三本しかない、と太宰は大笑いするのだ。酔うとそれが太宰の口癖になった。雌雄の分らない鶏も、酔後の彼の口癖だ。――そんなことで、その日も大笑いした。胸に憂悶があればこそ、こんな他愛もないことに笑い興じるのだ。
夜になって、臼井君が見えたので、だいぶ賑やかになった。私はもう可なり酔って、どんなことを話したかあまり覚えていない。ただ、私の酔後の癖として、眼の前にいる人の悪口を言ってそれを酒の肴にすることが多いので、
或 は臼井君に失礼なことばかり言ったかも知れない。
臼井君は、酒は飲むが、あまり酔わない。程よく帰って行った。
太宰も私も、だいぶ酒にくたぶれた。太宰はビタミンB1の注射をする。なんどか喀血したし、実は相当に体力も弱っているので、ビタミン剤などを常に飲んだり注射したりしているのである。注射はさっちゃんの役目だ。勇敢にさっとやってのける。ビタミンB1は、アンプル中の薬液の変質を防ぐために、酸性になされていて、それが可なり肉にしみる。さっちゃんが注射すると、痛い、と太宰は顔をしかめる。
「僕にさしてみたまい。痛くないようにしてみせる。」
皮下に針をさして、極めて徐々に薬液を注入する。
「どうだ、痛くないだろう。」
「うん。」太宰は頷く。
そこで私は、終り頃になって、急に強く注射する。
「ち、痛い。」そして大笑いだ。
さっちゃんは勇敢に注射するが、ただそれだけで、他事はもう鞠躬如 として太宰に仕えている。太宰がどんなに我儘 なことを言おうと、どんな用事を言いつけようと、片言の抗弁もしない。すべて言われるままに立ち働く。ばかりでなく、積極的にこまかく気を配って、身辺の面倒をみてやる。もし隙間風があるとすれば、その風にも太宰をあてまいとする。それは全く絶対奉仕だ。家庭外で仕事をする習慣のある太宰にとって、さっちゃんは最も完全な侍女であり看護婦であった。――家庭のことは、美知子夫人がりっぱに守ってくれる。太宰はただ仕事をすればよかったのだ。
そういう風で、太宰とさっちゃんとの間に、愛欲的なものの影を吾々 は少しも感じなかった。二人の間になにか清潔なものさえ吾々 は感じた。この感じは、誤ってるとは私は思わない。だから私は平気で二人を一室に宿泊させるのだった。――その夜も宿泊させた。
■「さっちゃん」こと、太宰の愛人・山崎富栄
翌朝、すべての用事をさっちゃんに言いつける太宰が、珍らしく、自分で出かけて行った。だいぶたってから、一束の花を持って戻って来た。白い花の群がっている数本の強い茎を中軸にして、
芍薬 の美しい赤い花が二輪そえてある。
「どうだ、これは僕でなくちゃ分らん、お嬢さんに似てるだろう。」
さっちゃんを顧りみて太宰は言う。照れ隠しらしい。これだけは自分で買って来たいと思ったのだ。そしてそれを、お嬢さんへと言って私に差出した。
私たちは残りのウイスキーを飲みはじめた。女手は女中一人きりなので、さっちゃんがまたなにかと立ち働く。そこへ、八雲から亀島君がやって来、筑摩の臼井君もまた立ち寄った。暫 くして、太宰は皆に護られて帰っていった。背広に重そうな兵隊靴、元気な様子はしているが、後ろ姿になにか疲れが見える。疲れよりも、憂鬱な影が見える。
それきり、私は太宰に逢わなかった。逢ったのは彼の死体にだ。――死は、彼にとっては一種の旅立ちだったろう。その旅立ちに、最後までさっちゃんが付き添っていてくれたことを、私はむしろ嬉しく思う。

■弔辞を読む井伏鱒二 1948年(昭和23年)6月21日、太宰の自宅で行われた告別式にて。
【了】
********************
【参考文献】
・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)
・志村有弘/渡部芳紀 編『太宰治大事典』(勉誠出版、2005年)
・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)
・河出書房新社編集部 編『太宰よ! 45人の追悼文集』(河出文庫、2018年)
・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)
※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。
********************
【太宰治39年の生涯を辿る。
"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】
【太宰治の小説、全155作品はこちら!】
【週刊 太宰治のエッセイ】市井喧争

今週のエッセイ
◆『
1939年(昭和14年)、太宰治 30歳。
1939年(昭和14年)10月下旬頃に脱稿。
『市井喧争』は、1939年(昭和14年)12月1日発行の「文藝日本」第一年第六号の「随筆特集」欄に発表された。この欄にはほかに「鳥の随筆」(岡田三郎)、「一章」(山崎剛平)、「残菊物語余談」(花柳章太郎)、「ちぎられる蘆」(清野重郎)、「雑談」(尾崎一雄)が掲載された。

■太宰が住んだ三鷹の借家の玄関
「
市井喧争 」
九月のはじめ、甲府からこの三鷹へ引越し、四日目の昼ごろ、百姓風俗の変な女が来て、この近所の百姓ですと嘘をついて、むりやり薔薇を七本、押売りして、私は贋物 だということは、わかっていたが、私自身の卑屈な弱さから、断り切れず四円まきあげられ、あとでたいへん不愉快な思いをしたのであるが、それから、ひとつき経って十月のはじめ、私は、そのときの贋 百姓の有様を小説に書いて、文章に手を入れていたら、ひょっこり庭へ、ごめん下さいまし、私は、このさきの温室から来ましたが、何か草花の球根でも、と言い、四十くらいの男が、おどおど縁先で笑っている。こないだの贋百姓とは、ちがう人であるが同じたぐいのものであろうと思い、だめですよ、このあいだも薔薇を八本植えられてしまいました、と私は余裕のある笑顔でもって言ったら、その男は、少し顔が蒼くなり、
「なんですか。植えられてしまった、とはどんなことですか。」と急に居直って、私にからんで来たのである。
私は恐ろしく、からだが、わくわく震えた。落ちつきを見せるために、机に頬杖をつき、笑いを無理に浮べて、
「いいえ、ね、その庭の隅に、薔薇が植えられて在るでしょう? それが、だまされて買ったんです。」
「私と、どんな関係があるんですか? おかしなことを言うじゃないですか。私の顔を見て、植えられたとは、おかしなことを言うじゃないですか。」
私も、笑わず、
「君のことを言ってるんじゃないよ。先日私は、だまされて不愉快だから、そのことを言っているのですよ。君は、そんな、ものの言いかたをしちゃ、いけないよ。」
「へん。こごとを聞きに来たようなものだ。お互い、一対一じゃねえか。五厘 でも、一銭でも、もうけさせてもらったら、私は商人だ。どんなにでも、へえへえしてあげるが、そうでもなけれあ、何もお前さんに、こごとを聞かされるようなことは、ねえんだ。」
「それあ、理屈だ。そんなら、僕だって理屈を言うが、君は、僕を訪ねて来たんじゃないか。」誰に断って、のこのこ、ひとの庭先なんかへ、やって来たんだ、と言おうと思ったが、あんまりそれは、あさましい理屈で、言うのを止めた。
「訪ねたから、それがどうしました。」商人は、私が言い澱 んでいるので、つけこんで来た。「私だって、一家のあるじだ。こごとなんて、聞きたくないや。だまされたなんて言うけれど、こうして植えて、たのしんでいるじゃないですか。」図星であった。私は、敗色が濃かった。
「それあ、たのしんでいる。僕は、四円もとられたんだぜ。」
「安いもんじゃないですか。」言下に反発して来る。闘志満々である。「カフェへ行って酒を呑むことを考えなさい。」失敬なことまで口走る。
「カフェなんかへは行かないよ。行きたくても、行けないんだ。四円なんて、僕には、おそろしく痛かったんですよ。」実相をぶちまけるより他は無い。
「痛かったかどうか、こっちの知ったことじゃないんです。」商人は、いよいよ勢を得て、へへんと私を嘲笑 した。「そんなに痛かったら、あっさり白状して断れば、よかったんだ。」
「それが僕の弱さだ。断れなかったんだ。」
「そんなに弱くて、どうしますか。」いよいよ私を軽蔑 する。「男一匹、そんなに弱くてよくこの世の中に生きて行けますね。」生意気なやつである。
「僕も、そう思うんだ。だから、これからは、要らないときには、はっきり要らないと断ろうと覚悟していたのだ。そこへ、君が来たというわけなんだ。」
「はははは、」商人は、それを聞いてひどく笑った。「そういうわけですか。なるほどねえ。」とやはり、いや味な語調である。「わかりました。おいとましましょう。こごとを聞きに来たんじゃないんだからなあ。一対一だ。そっくりかえっていることは無いんだ。」捨てぜりふを残して立ち去った。私はひそかに、ほっとした。
ふたたび、先日の贋百姓の描写に、あれこれと加筆して行きながら、私は、市井 に住むことの、むずかしさを考えた。
隣部屋で縫物をしていた妻が、あとで出て来て、私の応対の仕方の拙劣を笑い、商人には、うんと金のある振りを見せなければ、すぐ、あんなにばかにするものだ、四円が痛かったなど、下品なことは、これから、おっしゃらないように、と言った。
妻から見た『市井喧争 』
4円。現在の貨幣価値に換算すると、約4,800~5,900円に相当する薔薇を、自宅の庭に植えられた自身の経験を基に書かれた、今回のエッセイ「
エッセイ中に「私は、そのときの
エッセイや小説を読んでいると、コメディのようにも思えますが、実際のこの時の様子を、太宰の妻・津島美知子が記録していました。津島美知子の著書『回想の太宰治』から引用してみます。
三鷹移ってからはもう御崎町時代のように酔って義太夫をうなることもなくなり、緊張度が高まったように思う。
まだこの新開地の環境にも家にもなじまない引越し早々、「善蔵を思う」「市井喧争」に書かれたような小事件があった。あるとき花の苗を売り歩く男が庭に入ってきた、生垣がざっと境界になっているだけで誰でも何時でも庭に入ってこれる。それは郊外でよく見かける行商人で、べつに贋 百姓というわけではないが、特有の強引さで売りつけて、まごまごしているとそこらに植えてしまいそうな勢である。太宰はまだこの一種の押し売りを相手にしたことがなかったのだろう。机に向かって余念ないとき、突然鼻先に、見知らぬ男が現われたので動転して、喧嘩を売られたような応答をしたので先方もやり返し、険悪な空気になった。結局六本のバラの苗を植えて男は立ち去り、この苗はちゃんと根付いたのであるが、このとき私は太宰という人の、新しい一面を見たと思った。来客との話は文学か、美術の世界に限られていて、隣人と天気の挨拶を交すことも不得手なのである。ましてこのような行商人との応酬など一番苦手で、出会いのはじめから平静を失っている。このとき不意打ちだったのもまずかった。気の弱い人の常で、人に先手をとられることをきらう。それでいつも人に先廻りばかりし取越苦労するという損な性分である。
私はその後、この一件を書いた小説を読んで、さらに驚いた。あのとき一部始終を私は近くで見聞きしていた。私にとっての事実と太宰の書いた内容とのくい違い、これはどういうことなのだろう。偽りかまことかという人だ――と私は思った。
太宰が見ていた景色と、妻から見た景色は、少し異なっていたようです。
「太宰は私小説作家」と呼ばれたりもしますが、事実がどこまで「太宰風」にデフォルメされているのか、思いを巡らせながら作品を読んでみても面白いかもしれません。

■太宰と妻・津島美知子
【了】
********************
【参考文献】
・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)
・志村有弘/渡部芳紀 編『太宰治大事典』(勉誠出版、2005年)
・津島美知子『回想の太宰治』(講談社文芸文庫、2008年)
・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)
・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)
・HP「日本円消費者物価計算機」
※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。
********************
【太宰治39年の生涯を辿る。
"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】
【太宰治の小説、全155作品はこちら!】
【週刊 太宰治のエッセイ】ラロシフコー

今週のエッセイ
◆『ラロシフコー』
1939年(昭和14年)、太宰治 30歳。
1939年(昭和14年)5月中旬か下旬頃に脱稿。
『ラロシフコー』は、1939年(昭和14年)7月1日発行の「作品」第十巻第七号に発表された。
「ラロシフコー」
その高橋五郎という人は、他にどんな仕事をした人か、私は知らない。この人は、大正二年にラロシフコーを訳している。「寸鉄」という題で、出版している。大正二年といえば、私など、四、五歳のころで、そのころ此 の本の出版が、どんな反響を呼んだか、知る由もないが、けれども、序文を見ると、たいへんな意気込である。
「仏蘭西 文学の旺盛時代たる路易 第十四世の朝に於て、突如として一世の耳目を聳動 し来れる一書あり、其の簡浄痛快にして霊犀奇警 なる人世批評 は、天下驚畏の中心となれり、本書是れ也。其 著者を誰とかする、即ち当時廷臣とし、軍人とし、政治家として夙 に盛名あるも、未だ文筆の人としては左までに顕 われざりしラロシフコー公爵其人 なりとす。云々。」と、たくさん書いている。おしまいのほうに、「我国人の間にも豈 之が紹介の要無しと言わんや、本書の訳ある徒爾 ならざるを信ず。」と揚言して在るところから見ても、この訳書が、日本で最初のラロシフコー紹介では無かったか、と思われる。高橋五郎という人の名前はなんだか聞いたことのあるような気もするのであるが、はっきりしない。
この本には、「寸鉄」と表題を打たれ、その傍題として、(又名、人生裏面観)と印刷されて在る。訳文は、豪邁 である。たとえば、
「寵 を蒙 むる者を憎むは、己れ自ら寵を望む也、之を有せざる者の怒るは、之を有する者を侮蔑して自ら慰安する耳 。吾人は世人の尊敬を彼等に牽 く所の者を彼等より奪わんと欲して能 わざるが故に、己れの尊敬を彼らに拒む也。」いかにも、「廷臣とし、軍人とし、政治家として夙 に盛名ある」ラロシフコー公爵その人の息吹が感ぜられる尊厳盛大の、そうして多少わからずや では、なかったのか、と思った。この訳文は、その意味で、まさに適訳なのかも知れない、と思った。
身もふたもない言いかた。そんな言いかたを体得して、弱いしどろもどろの人を切りまくって快 しとしている人が、日本にも、ずいぶんたくさん在る。いや、日本人は、そんな哲学で育てられて来た。い、犬も歩けば棒に当る。ろ、論より証拠。は、花よりだんご。それが日本人のお得意の哲学である。ラロシフコーなど読まずとも、所謂 、「人生裏面観」は先刻すでに御承知である。真理は、裏面にあると思っている。ロマンチックを、頭の悪さと解している。けれども、少しずつ舞台がまわって、「聖戦」という大ロマンチシズムを、理解しなければならなくなって、そんなにいつまでも、「人をして一切の善徳と悪徳とを働かしむるものは利害の念なり。」など喝破して、すまして居られなくなったであろう。浪漫派哲学が、少しずつ現実の生活に根を下 し、行為の源泉になりかけて来たことを指摘したい。ラロシフコーは、すでに古いのである。
太宰とラ・ロシュフコー
今回のエッセイ『ラロシフコー』で、太宰が語る「ラロシフコー」とは、フランスの貴族で、モラリスト文学者である、ラ・ロシュフコー公爵フランソワ6世(1613~1680)のことです。

■フランソワ・ド・ラ・ロシュフコー(1613~1680)
ラ・ロシュフコーは、名門貴族の生まれで、多くの戦いに参加した後、主著である『考察あるいは教訓的格言・
ラ・ロシュフコーの作品に見られる辛辣な人間観察には、カトリック教会の聖職者にしてフランスの政治家、ルイ13世の宰相を務めたリシュリュー(1585~1642)と対立して2年間の謹慎処分を受けたことや、フランスにおける最後の貴族の反乱である「フロンドの乱(1648~1653)」において、フランスの政治家で枢機卿(カトリック教会における教皇の最高顧問)であるジュール・マザラン(1602~1661)と対立したことで味わった苦難が反映されているとも言われています。

■フロンドの乱(1648~1653) フランス中央政府(ジュール・マザラン)と貴族・民衆(コンデ公)が対立した。フランスにおける貴族の反乱としては最後のもので、貴族勢力は圧倒され、絶対王政の確立に繋がった。フロンドとは、当時流行していた投石機のことで、パリの民衆がマザラン邸を目掛けて投石したことから、「フロンドの乱」と呼ばれるようになった。
ラ・ロシュフコーの生きた17世紀のフランス、14世が支配するヴェルサイユ宮殿の中の宮廷社会では、行動や衣服が明確に決められ、外見が全てという「外見の文化」の世界でした。しかし一方で、外見と中身、言葉と心の中の思いのずれも意識されましたが、「外見の文化」そのものである宮廷社会では、外見から中身を読み取る必要がありました。ラ・ロシュフコーの『考察あるいは教訓的格言・
われわれの徳行は、往々にして偽装した不徳にすぎない。
われわれは、あまりにも他人の前に自分を偽装するのに慣れているので、しまいには自分の前にまで自分を偽装するようになる。
恋を定義するのは難しい。強いて言えば、恋は心において支配の情熱、知においては共感であり、そして肉体においては、大いにもったいをつけて愛する人を所有しようとする、隠微な欲望にほかならない。
慎ましさとは、妬みや軽蔑の的になることへの恐れである。幸福に酔いしれれば必ずそういう目にあうからだ。それはわれわれの精神のくだらない虚勢である。さらにまた、栄達を極めた人びとの慎ましさは、その栄位をものともしないほど偉い人間に自分を見せようとする欲望なのである。
これに対して太宰は、「ラロシフコーなど読まずとも、
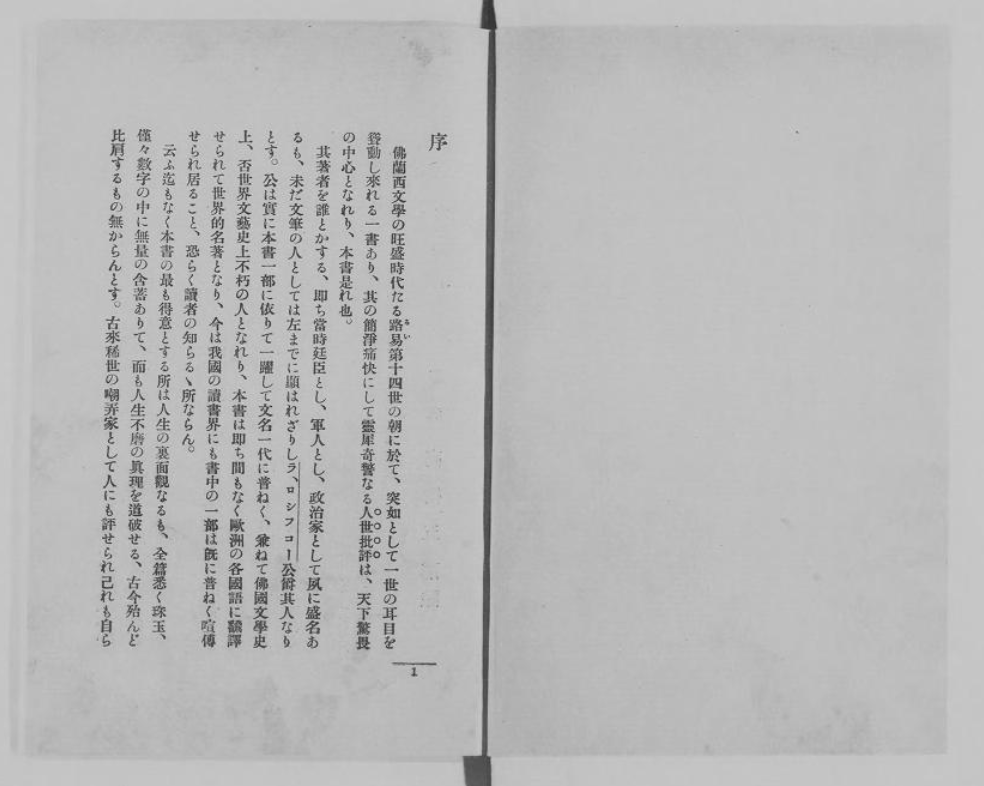
■太宰が引用している『寸鉄』(高橋五郎 訳)の「序文」 国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧が可能です。
太宰は、小説『風の便り』の中で、次のように書いています。
(前略)あいつは厭な奴だと、たいへん好きな癖に、わざとそう言い変えているような場合が多いので、やり切れません。思惟と言葉との間に、小さい歯車が、三つも四つもあるのです。けれども、この歯車は微妙で正確な事も信じていて下さい。私たちの言葉は、ちょっと聞くとすべて出鱈目の放言のように聞えるでしょうが、しさいにお調べになったら、いつでもちゃんと歯車が連結されている筈です。
太宰は「思惟と言葉との間」に「三つも四つもある」「小さい歯車」について、「微妙で正確な事も信じていて下さい」と言います。表に隠された裏だけではなく、表の中にも真理がある、ということでしょうか。
今回のエッセイで批判しているラ・ロシュフコーですが、太宰は他の作品でもラ・ロシュフコーを引用しています。
『無間奈落』
「『女は必ず淫猥である』というようなことをラ・ロシフコオが言ってあったっけ。」
『正義と微笑』
「『吾人が小過失を懺悔するは、他に大過失なき事を世人に信ぜしめんが為のみ』――ラ・ロシフコオ」
「己れ只一人智からんと欲するは大愚のみ。(ラ・ロシフコオ)」
太宰にとって「相手の言葉の裏を読む」ということは、その39年の人生の中で、悩み続けた大きな価値観の1つだったのではないでしょうか。

【了】
********************
【参考文献】
・東郷克美 編『太宰治事典』(學燈社、1994年)
・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)
・志村有弘/渡部芳紀 編『太宰治大事典』(勉誠出版、2005年)
・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)
・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)
・HP「 言葉の裏を読む 太宰治とラ・ロシュフコー」(LA BOHEME GALANTE)
・HP「国立国会図書館デジタルコレクション」
※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。
********************
【太宰治39年の生涯を辿る。
"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】
【太宰治の小説、全155作品はこちら!】
【週刊 太宰治のエッセイ】女人創造

今週のエッセイ
◆『
1938年(昭和13年)、太宰治 29歳。
1938年(昭和13年)9月末か10月初めの頃に脱稿。
『女人創造』は、1938年(昭和13年)11月1日発行の「日本文學」第一巻第七号の「秋の随想集」欄に発表された。この欄には、ほかに「大島紀行」(中村地平)、「秋と若い女」(田島準子)が掲載された。

■『女性』初版復刻版 1942年(昭和17年)6月30日付、博文館より刊行された。『十二月八日』『女生徒』『葉桜と魔笛』『きりぎりす』『燈籠』『誰も知らぬ』『皮膚と心』『恥』『待つ』所収。写真は、1992年(平成4年)、日本近代文学館より刊行された「名著初版本復刻 太宰治文学館」。
「
女人創造 」
男と女は、ちがうものである。あたりまえではないか、と失笑し給うかも知れぬが、それでいながら、くるしくなると、わが身を女に置きかえて、さまざまの女のひとの心を推察してみたりしているのだから、あまり笑えまい。男と女はちがうものである。それこそ、馬と火鉢ほど、ちがう。思いにふける人たちは、これに気がつくこと、甚 だおそい。私も、このごろ、気がついた。名前は忘れたが或る外国人のあらわしたショパン伝を読んでいたら、その中に小泉八雲の「男は、その一生涯に、少くとも一万回、女になる。」という奇怪な言葉が引用されていたが、そんなことはないと思う。それは、安心していい。
日本の作家で、ほんとうの女を描いているのは、秋江 であろう。秋江に出て来る女は、甚だつまらない。「へえ。」とか、「そうねえ。」とか呟いているばかりで、思索的でないこと、おびただしい。けれども、あれは、正確なのである。謂わば、なつかしい現実である。
江戸の小咄 にも、あるではないか。朝、垣根越しにとなりの庭を覗き見していたら、寝巻姿のご新造が出て来て、庭の草花を眺め、つと腕をのばし朝顔の花一輪を摘み取った。ああ風流だな、と感心して見ていたら、やがて新造は、ちんとその朝顔で鼻をかんだ。
モオパスサンは、あれは、女の読むものである。私たち一向に面白くないのは、あれには、しばしば現実の女が、そのままぬっと顔を出して来るからである。頗 る、高邁 でない。モオパスサンは、あれほどの男であるから、それを意識していた。自分の才能を、全人格を厭悪 した。作品の裏のモオパスサンの憂鬱 と懊悩 は、一流である。気が狂った。そこにモオパスサンの毅然 たる男性が在る。男は、女になれるものではない。女装することは、できる。これは、皆やっている。ドストエフスキイなど、毛臑 まるだしの女装で、大真面目である。ストリンドベリイなども、ときどき熱演のあまり鬘 を落して、それでも平気で大童 である。
女が描けていない、ということは、何も、その作品の決定的な不名誉ではない。女を描けないのではなくて、女を描かないのである。そこに理想主義の獅子奮迅が在る。美しい無智がある。私は、しばらく、この態度に拠 ろうと思っている。この態度は、しばしば、盲目に似ている。時には、滑稽 でさえある。けれども、私は、「あらまあ、しばらく。」なぞという挨拶にはじまる女人の実態を活写し得ても、なんの感激も有難さも覚えないのだから、仕方がないのである。私は、ひとりになっても、やはり、観念の女を描いてゆくだろう。五尺七寸の毛むくじゃの男が、大汗かいて、念写する女性であるから笑い上戸 の二、三人の人はきっと腹をかかえて大笑いするであろう。私自身でさえ、少し可笑 しい。男の読者のほとんど全部が、女性的という反省に、くるしめられた経験を。お持ちであろう。けれども、そんなときには、女をあらためて、も一度見ることである。つくづくその女の動きを見ているうちに、諸君は、安心するであろう。ああ僕は、女じゃない。女は、瞑想 しない。女は、号令しない。女は、創造しない。けれども、その現実の女を、あらわに軽蔑 しては、間違いである。こんなことは、書きながら、顔が赤くなって来て、かなわない。まあ、やさしくしてやるんだね。
絶望は、優雅を生む。そこには、どうやら美貌 のサタンが一匹住んでいる。けれども、その辺のことは、ここで軽々しく言い切れることがらでない。
こんな、とりとめないことを、だらだら書くつもりでは、なかったのである。このごろまた、小説を書きはじめて、女性を描くのに、多少、秘法に気がついた。私には、まだ、これといって誇示できるような作品がないから、あまり大きいことは言えないが、それは、ちょっと、へんな作法である。言い出そうとして、流石 に、口ごもるのである。言っては、いけないことかも知れない。へんなものである。なに、まえから無意識にやっていたのを、このごろ、やっと大人になって、それに気づいたというだけのことかも知れない。言い出せば、それは、あたりまえのことで、なあんだということになるのかも知れないが、下手に言い出して曲解され、損をするのは、いやだ。やはり、黙っていよう。
「叡智 は悪徳である。けれども作家は、これを失ってはならぬ。」
太宰の女性独白体
太宰ならではの文体の形式に「女性独白体」があります。
太宰の「女性独白体」は、1937年(昭和12年)に書かれた『燈籠』で初めて見られました。今回紹介したエッセイ『女人創造』が書かれた時点では、『燈籠』の1作のみでしたが、最終的には『燈籠』含め、全16作品が執筆されました。太宰の小説作品は、全部で155作品あるので、全作品の1割強が「女性独白体」で書かれているということになります。
「女性独白体」で書かれた16作品は、以下の通りです。(※初出雑誌掲載順に並んでいます。作品名の後の年号は、執筆された年です。)
【前期】
・『燈籠』・・・・・1937年(昭和12年)【中期】
・『女生徒』・・・・1939年(昭和14年)
・『葉桜と魔笛』・・1939年(昭和14年)
・『皮膚と心』・・・1939年(昭和14年)
・『誰も知らぬ』・・1940年(昭和15年)
・『きりぎりす』・・1940年(昭和15年)
・『千代女』・・・・1941年(昭和16年)
・『恥』・・・・・・1941年(昭和16年)
・『待つ』・・・・・1942年(昭和17年)
・『十二月八日』・・1941年(昭和16年)
・『雪の夜の話』・・1944年(昭和19年)【後期】
・『貨幣』・・・・・1945年(昭和20年)
・『ヴィヨンの妻』・1947年(昭和22年)
・『斜陽』・・・・・1947年(昭和22年)
・『おさん』・・・・1947年(昭和22年)
・『饗応夫人』・・・1947年(昭和22年)
「女性独白体」の文体は、太宰らしい表現方法のように感じられますが、その執筆時期のほとんどが、中期~後期に集中しているのは、一体なぜなのでしょう。
太宰は、前期の作品において、自分の気持ちを素直に小説に記しますが、彼の表現方法は、必ずしも快く世の中に受け入れられませんでした。
1940年(昭和15年)に執筆された作品『春の盗賊』で、太宰は次のように書いています。
(前略)かなしいかな、この日頃の私には、それだけの余裕さえ無かった。おのれの憤怒と絶望を、どうにか素直に書きあらわせた、と思ったとたん、世の中は、にやにや笑って私の
額 に、「救い難き白痴」としての焼印を、打とうとして手を挙げた。いけない! 私は気づいて、もがき脱れた。危いところであった。打たれて、たまるか。私は、いまは、大事のからだである。真実、そのものを愛し、そのもののために主張してあげたい、その価値を有する弱い尊いものをさえ、私は、いまは見つけたような気がしている。私は、いまは、何よりも先ず、自身の言葉に、権威を持ちたい。何を言っても気ちがい扱いで、相手にされないのでは、私は、いっそ沈黙を守る。激情の果の、無表情。あの、微笑の、能面 になりましょう。この世の中で、その発言に権威を持つためには、まず、つつましい一般市井人 の家を営み、その日常生活の形式に於いて、無欲。
「おのれの憤怒と絶望を、どうにか素直に書きあらわせた」と思っていた太宰ですが、「世の中は、にやにや笑って」太宰の「
太宰は、何とかその状況から逃れようと、もがき苦しみ、「この世の中で、その発言に権威を持つ」ことを目標に掲げ、「一般
最初の「女性独白体」作品で、前期最後の作品である『燈籠』が脱稿されたのは、1937年(昭和12年)8月23日、24日頃だと推測されています。これは、同年3月中旬、上京後7年間生活を共にした最初の妻・
『燈籠』は、1936年(昭和11年)11月24日に脱稿された『HUMAN LOST』以来、約9ヶ月ぶりに執筆された作品であり、太宰が、小説家として再起を懸けて臨んだ作品であることが想像できます。
『燈籠』の次に「女性独白体」で執筆されたのは、2年後の1939年(昭和14年)、『女生徒』です。同年1月には

■太宰と津島美知子
『女生徒』は、「『女生徒』のような作品に出会えることは、時評家の偶然の幸福なのである。そのために、賛辞が或いは多少の誇張にわたるのは、文学を愛する者の当然の心事である。(中略)『女生徒』を借りて作者自身の女性的なるものすぐれていることを現した、典型的な作品である」(川端康成)、「最近のものでは、『女生徒』が一ばん出色のものだった」(浅見

■「女性独白体」作品の名を冠した単行本 1992年(平成4年)、日本近代文学館より刊行された「名著初版本復刻 太宰治文学館」より。
【了】
********************
【参考文献】
・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)
・志村有弘/渡部芳紀 編『太宰治大事典』(勉誠出版、2005年)
・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)
・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)
※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。
********************
【太宰治39年の生涯を辿る。
"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】
【太宰治の小説、全155作品はこちら!】
【週刊 太宰治のエッセイ】一歩前進二歩退却

今週のエッセイ
◆『一歩前進二歩退却』
1938年(昭和13年)、太宰治 29歳。
1938年(昭和13年)7月上旬に脱稿。
『一歩前進二歩退却』は、1938年(昭和13年)8月1日発行の「文筆」の「随想」欄に発表された。この欄には、ほかに「作家の手帖」(渋川驍)、「ジイドの旅行記」(丸岡明)、「山歩き」(田畑修一郎)、「戸を叩く」(長見義三)、「農民小説の方向」(佐藤民宝)、「雨降りつゞき」(庫田重義)、「北京だより」(秋沢三郎)、「金さんのあそび」(中村俊定)、「島へ来た友人」(浅沼悦)、「井之頭」(山崎剛平)、「憂鬱な話」(井上友一郎)、「子供の作文」(中谷孝雄)が掲載された。
「一歩前進二歩退却」
日本だけではないようである。また、文学だけではないようである。作品の面白さよりも、その作家の態度が、まず気がかりになる。その作家の人間を、弱さを、嗅ぎつけなければ承知できない。作品を、作家から離れた署名なしの一個の生き物として独立させては呉 れない。三人姉妹を読みながらも、その三人の若い女の陰に、ほろにがく笑っているチェホフの顔を意識している。この鑑賞の仕方は、頭のよさであり、鋭さである。眼力 、紙背 を貫くというのだから、たいへんである。いい気なものである。鋭さとか、青白さとか、どんなに甘い通俗的な概念であるか、知らなければならぬ。
可哀そうなのは、作家である。うっかり高笑いもできなくなった。作品を、精神修養の教科書として取り扱われたのでは、たまったものじゃない。猥雑なことを語っていても、その話手がまじめな顔をしていると、まじめな顔をしているから、それは、まじめな話である。笑いながら厳粛のことを語っていても、それは、笑いながら語っているから、ばかばかしい嘘言である。おかしい。私が夜おそく通りがかりの交番に呼びとめられ、いろいろうるさく聞かれるから、すこし高めの声で、自分は、自分は、何々であります、というあの軍隊式の言葉で答えたら、態度がいいとほめられた。
作家は、いよいよ窮屈である。何せ、眼光紙背 に徹する読者ばかりを相手にしているのだから、うっかりできない。あんまり緊張して、ついには机のまえに端座したまま、そのまま、沈黙は金、という格言を底知れず肯定している、そんなあわれな作家さえ出て来ぬともかぎらない。
謙譲を、作家のみに要求し、作家は大いに恐縮し、卑屈なほどへりくだって、そうして読者は旦那である。作家の私生活、底の底まで剥 ごうとする。失敬である。安売りしているのは作品である。作家の人間までを売ってはいない。謙譲は、読者にこそ之を要求したい。
作家と読者は、もういちど全然あたらしく地割りの協定をやり直す必要がある。
いちばん高級な読書の仕方は、鷗外でもジッドでも尾崎一雄でも、素直に読んで、そうして分相応にたのしみ、読み終えたら涼しげに古本屋へ持って行き、こんどは涙香の死美人と交換してきて、また、心ときめかせて読みふける。何を読むかは、読者の権利である。義務ではない。それは、自由にやって然 るべきである。
太宰の研究者・長篠康一郎
私が、今回紹介したエッセイの冒頭「作品を、作家から離れた署名なしの一個の生き物として独立させては

■
昨年、更新していた「日めくり太宰治」でも、多くの記事を執筆する際に、その研究成果を引用、参考にさせて頂きました。
長篠は、自ら標榜する「実証的研究」によって、世間一般に定着する太宰のマイナスイメージを全面的に否定しました。全国各地の太宰ゆかりの地を徹底的に取材、時には自ら人体実験を行い、麻薬中毒や左翼運動への関与、数度にわたって行われた自殺・心中未遂など、太宰の死の直後から伝えられてきた「虚像」をひっくり返しました。「太宰文学研究会」も主催し、会員の研究成果を発表する場としていました。
1948年(昭和23年)6月13日、山崎富栄との心中事件も、富栄の主導による他殺説(無理心中説)が「定説」と言われる中、真っ向から否定し、2人は合意の下で玉川上水に入水したと明言しました。
また、私小説作家だと思われていた太宰の小説が「実は虚構の物語ではないか」という観点から、実証研究を行いました。それまでの『太宰治全集』などに収録されていた「太宰治の年譜」は、太宰の作品の記述をそのまま年譜内にも取り込んだものでしたが、先達の研究成果や自分の調査結果を示しながら、すみやかな年譜の訂正を求めました。
この年譜の訂正にかかわる活動が、エッセイの冒頭「作品を、作家から離れた署名なしの一個の生き物として独立させては

■長篠の著書 左から『山崎富栄の生涯 ー太宰治その死と真実ー』(大光社、1967年)、『太宰治七里ケ浜心中』(広論社、1981年)、『太宰治水上心中』(広論社、1982年)、『太宰治武蔵野心中』(広論社、1982年)。
この「虚像」や「定説」を作り上げて来たのは、中央文壇の実力者や太宰研究の権威者とその取り巻き連中でした。自分たちの作り上げたイメージを「実証的研究」により否定する長篠を、彼らは忌み嫌い、研究活動を妨害したり、脅迫したりしました。職場で勤務中にも電話がかかってきたり、家族や太宰文学研究会の会員にも被害が及んだため、長篠は会社を退職し、研究会は解散となりました。
素晴らしい研究成果を残しているにもかかわらず、インターネット検索で長篠に関する情報をあまり得ることが出来ないのは、こういった経緯があったためでしょうか。
しかし、長篠は、これで太宰研究を諦めるようなことはせず、再び研究会を立ち上げ、雑誌などで執筆活動を再開させました。
また、長篠は、太宰を愛し支えた女性の地位向上にも努め、1966年(昭和41年)から2002年(平成14年)まで、太宰と、彼を愛し支えた4人の女性(山崎富栄、田部あつみ、小山初代、太田静子)を供養する「白百合忌」も行います。「白百合忌」は、太宰と富栄の意志を汲み、6月13日に行われていました。
長篠は、2002年(平成14年)、難病・パーキンソン病に侵されました。病気は急激に進行し、容赦なく体力を奪っていったそうです。自らの回復を信じ、社会復帰を目指していたといいます。しかし、それが叶うことはありませんでした。
氏が遺した研究成果は、決して真似できるものではなく、今後の太宰研究にも大いに活用されていくことでしょう。
【長篠康一郎の著書一覧】
・『山崎富栄の生涯 ー太宰治その死と真実ー』(大光社、1967年)
・『 愛は死と共に ー太宰治との愛の遺稿集ー』(虎見書房、1968年)
・『人間太宰治の研究Ⅰ』(虎見書房、1968年)
・『人間太宰治の研究Ⅱ』(虎見書房、1969年)
・『人間太宰治の研究Ⅲ』(虎見書房、1970年)
・『雨の玉川心中 ー太宰治との愛と死のノートー』(真善美研究所、1977年)
・『太宰治七里ケ浜心中』(広論社、1981年)
・『太宰治文学アルバム』(広論社、1981年)
・『太宰治武蔵野心中』(広論社、1982年)
・『太宰治文学アルバム ー女性篇ー』(広論社、1982年)
・『太宰治水上心中』(広論社、1982年)
・『太宰治との愛と死のノート ー雨の玉川心中とその真実ー』(学陽書房女性文庫、1995年)

■長篠直筆の原稿(複写)
【了】
********************
【参考文献】
・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)
・太宰文学研究会 編『 追悼 長篠康一郎 ー太宰治に捧げた生涯ー』(彩流社、2009年)
・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)
・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)
※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。
********************
【太宰治39年の生涯を辿る。
"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】
【太宰治の小説、全155作品はこちら!】
【週刊 太宰治のエッセイ】答案落第

今週のエッセイ
◆『答案落第』
1938年(昭和13年)、太宰治 29歳。
1938年(昭和13年)5月下旬頃に脱稿。
『答案落第』は、1938年(昭和13年)7月1日発行の「月刊文章」第四巻第七号の「私の小説修業」欄に発表された。
「答案落第」
「小説修業に就いて語れ。」という出題は、私を困惑させた。就職試験を受けにいって、小学校の算術の問題を提出されて、大いに狼狽している姿と似ている。円の面積を算出する公式も、鶴亀算の応用問題の式も、甚だ心もとなくいっそ代数でやればできるのだが、などと青色吐息の態 とやや似ている。
いろいろ複雑にくすぐったく、私は、恥ずかしい思いである。
スタートラインに並んで、未だ出発の合図のピストルの鳴らされぬまえに飛び出し、審判の制止の声も耳にはいらず、懸命にはしってはしってついに百米 、得意満面ゴールに飛び込み、さて写真班のフラッシュ待ちかまえ、にっと笑ってみるのだが、少し様子がちがって、一つの喝采もなし、満場の人、みな気の毒そうにその選手の顔を見ている。選手はじめて、はっとおのれの失敗に気づいて、恥ずかしいとも、くるしいとも、なんとも、どうも話にならない。
ふたたび私は、すごすご出発点に引返して、全身くたくたに疲れ、ぜいぜい荒い息を吐きながら、スタートラインに並んだ。フライイング犯した罰として、他の選手よりは一米 うしろの地点から走らなければならない。「用意!」審判の冷酷な声が、ふたたび発せられる。
私は、思いちがいしていた。このレエスは百米 競争では、なかったのだ。千米 、五千米 、いやいや、もっとながい大マラソンであった。
勝ちたい。醜くあせって全精力つかいはたして、こんなに疲れてしまっているが、けれども、私は選手だ。勝たなければ生きていけない単純な選手だ。誰か、この見込みの少い選手のために、声援を与える高邁 の士はいないか。
おととしあたり、私は私の生涯にプンクトを打った。死ぬと思っていた。信じていた。そうなければかなわぬ宿命を信じていた。自分の生涯を自分で予言した。神を冒したのである。
死ぬと思っていたのは、私だけではなかった。医者も、そう思っていた。家人も、そう思っていた。友人も、そう思っていた。
けれども、私は、死ななかった。私は神のよほどの寵児 にちがいない。望んだ死は与えられず、そのかわり現世の厳粛な苦しみを与えられた。私は、めきめき太った。愛嬌もそっけない、ただずんぐり大きい醜貌 の三十男にすぎなくなった。この男を神は、世の嘲笑と指弾と軽蔑と警戒と非難と蹂躙 と黙殺の炎の中に投げ込んだ。男はその炎の中で、しばらくもそもそしていた。苦痛の叫びは、いよいよ嘲笑の声を大にするだけであろうから、男は、あらゆる表情と言葉を殺して、そうして、ただ、いも蟲 のように、もそもそしていた。おそろしいことには、男は、いよいよ丈夫になり、みじんも愛くるしさがなくなった。
まじめ。へんに、まじめになってしまった。そうして、ふたたび出発点に立った。この選手には、見込みがある。競争は、マラソンである。百米 、ニ百米 の短距離レエスでは、もう、この選手、全然見込みがない。足が重すぎる。見よ、かの鈍重、牛の如き風貌を。
変れば変るものである。五十米 レエスならば、まず今世紀、かれの記録を破るものはあるまい、とファン囁き、選手自身もひそかにそれを許していた、かの俊敏はやぶさの如き太宰治とやらいう若い作家の、これが再生の姿であろうか。頭はわるし、文章は下手、学問は無し、すべてに無器用、熊の手さながら、おまけに醜貌、たった一つの取り柄は、からだの丈夫なところだけであった。
案外、長生きするのではないか。
こんな、ばかばなしをしていたのでは、きりがない。何かひとつ、実 になる話でもしようかね。実になる、ならない、もへんなもので、むかし発電機の発明をして得々としていたところ、一貴婦人から、けれども博士、その電気というものが起ったからって、それがどうなるのですの? と質問され、博士大いに閉口して、奥さま、生れたばかりの赤ん坊に、おまえは何を建設するのだい? と質問してみて下さい、と答えて逃げ去ったとかいう話があるけれども、何千年まえの世界には、どんな動物がいたか、一億年のちにはこの世界はどんなになるか、そんな話は、いったい実になるものかどうか。私は実になる話だと思っているが。
ヴァニティ。この強靭をあなどってはいけない。虚栄は、どこにでもいる。僧房の中にもいる。牢獄の中にもいる。墓地にさえ在る。これを、見て見ぬふりをしては、いけない。はっきり向き直って、おのれのヴァニティと対談してみるがいい。私は、人の虚栄を非難しようとは思っていない。ただ、おのれのヴァニティを鏡にうつしてよく見ろ、というのである。見た、結果はむりに人に語らずともよい。語る必要はない。しかし、いちどは、はっきり、合せ鏡して見とどけて置く必要は、ある。いちど見た人は、その人は、思案深くなるだろう。謙譲になるだろう。神の問題を考えるようになるだろう。
重ねていう。実はヴァニティを悪いものだとは言っていない。それは或る場合、生活意欲と結びつく。高いリアリティとも結びつく。愛情とさえ結びつく。私は、多くの思想家たちが、信仰や宗教を説いても、その一歩手前の現世のヴァニティに莫迦 正直に触れていないことを不思議がっているだけである。パスカルは、少々。
ヴァニティは、あわれなものである。なつかしいものである。それだけ、閉口なものである。
ながいことである。大マラソンである。いますぐいちどに、すべて問題を解決しようと思うな。ゆっくりかまえて、一日一日を、せめて悔いなく送りたまえ。幸福は、三年おくれて来る、とか。
太宰、東京帝国大学の選抜試験
エッセイのタイトル『答案落第』にちなんで、今回は、太宰の東京帝国大学受験について紹介します。
1930年(昭和5年)3月13日、当時20歳の太宰は、東京帝国大学の
私は昭和五年に
弘前 の高等学校を卒業し、東京帝大の仏蘭西文科に入学した。仏蘭西語を一字も解し得なかったけれども、それでも仏蘭西文学の講義を聞きたかった。辰野隆 先生を、ぼんやり畏敬 していた。

■辰野隆 1955年(昭和30年)撮影。
「仏蘭西文学の講義を聞きたかった」と書く太宰ですが、弘前高等学校で太宰の1年先輩だった
(前略)太宰は高校を卒業すると東大文学部のフランス文学科に入った。フランス文学科に入るひとは、大体高校時代文化丙類に籍を置いていたひとである(著者注・太宰は高校時代、文化甲類に籍を置いていた)。そうでなければ、例えば故中島健蔵氏のように、在籍していた松本高校ではフランス語を教えていなかったが、教会のフランス人の牧師のもとに出入りして、みっちりフランス語を修習していたひとに限られるのである。
フランス語を全然知らない太宰が、仏文科を志望するのははじめから無茶であった。私が太宰に、どうして仏文科などへ入るのかときいたときの彼の答は、東大仏文科という肩書が、今のことばで言えば、ひじょうに、かっこいいという単純なものであった。たとえ中退しても仏文科の方が、谷崎潤一郎の国文科中退よりもイキだというのである。それともう一つ大きな動機は、そのころ東大文学部の英文科や国文科などには入学試験があったが、仏文科は、志望者が定員不足で無試験であった。そういうことで弘前高校からは太宰のほかにもうひとり、あまり勉強家とはいえないスポーツマン(著者注・三戸斡夫 のこと)が仏文科をねらった。ただどういう風のふきまわしか、昭和五年というその年には仏文科でもフランス語の試験があった。
■弘前高等学校3年生の太宰と平岡敏男 弘前の喫茶店「みみづく」の前にて。目算がはずれた太宰らふたりは試験場で手を挙げて、正直に試験官に事情をはなした。その試験官は仏文科の主任教授故辰野隆博士であった。この一風変ったイキな教授は、苦笑したものの、格別の配慮で、ふたりの入学を認めてくれたのである。
太宰はそれでも、はじめて、フランス語を勉強するつもりで、アテネ・フランセに通ったりしていた。しかし間もなく文学活動を続ける一方左翼活動にもかかわりをもつようになって、フランス語を初歩から習う根気を失ってしまった。
東京帝大に、安田善次郎氏の寄附により、1925年(大正14年)に竣工した大講堂(安田講堂)。東大紛争で、全共闘の学生らがバリケードを築いて立て籠もり、警察側と激しく戦ったことで有名ですが、太宰が東京帝大に入学したのは、竣工の5年後。太宰もこの大講堂を見ていたのでしょう。

■東京帝大の安田講堂 太宰が入学した1930年(昭和5年)に撮影。
太宰が卒業できたかどうかについては、【日めくり太宰治】の記事で紹介していますので、ぜひ併せてご覧ください。
【了】
********************
【参考文献】
・山内祥史 編『太宰治に出会った日―珠玉のエッセイ集』(ゆまに書房、1998年)
・『太宰治全集 11 随想』(筑摩書房、1999年)
・志村有弘/渡部芳紀 編『太宰治大事典』(勉誠出版、2005年)
・山内祥史『太宰治の年譜』(大修館書店、2012年)
・田村茂 写真『素顔の文士たち』(河出書房新社、2019年)
・HP「東京大学」
※モノクロ画像は、上記参考文献より引用しました。
********************
【太宰治39年の生涯を辿る。
"太宰治の日めくり年譜"はこちら!】
【太宰治の小説、全155作品はこちら!】





